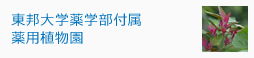ゾウリムシを使った利尿薬の作用についての実験
基礎生物実習の一部を紹介します。
ゾウリムシの収縮胞の観察
ゾウリムシを顕微鏡(40倍)で観察したもの。
さかんに動き回っています。動きが早くて、倍率を高くできないので、これでは細胞内の小器官を識別できそうもありません。
ニッケルで麻酔をかけて、動きを弱めたところ(40倍)。
ニッケルイオンでゾウリムシの繊毛の動きを弱めることができます。これなら顕微鏡の倍率を高くできそうです。
倍率を400倍にしたところ。
しばらく瞬きをしないで、観察してみると、丸い器官がだんだん大きくなった後にキュッと収縮するのがわかります。これが収縮胞です。収縮してから、次の収縮までの秒数を測ってみると、だいたい8秒くらいのようです。
マンニトールの効果
マンニトール(50μmol/L)で外液の浸透圧を高くしたところ(400倍)。
収縮してから次の収縮までの秒数は、マンニトールを入れると長くなりました。実験はこれで終わりです。
解説
この実験で使ったマンニトールは、「浸透圧性利尿薬」として日本薬局方に収載されている医薬品です。静脈注射して血液の浸透圧を高くすることで、体内の水分の移動に影響を与えます。適応症は、脳圧降下、眼圧降下です。
収縮胞は、体内に浸透してきた水分を一時保存し、満たされると収縮して外へ出す器官です。ゾウリムシを使った実験で、マンニトールの薬理作用が目に見えてわかります。もっと知りたければ、いちど私たちと一緒に実験してみませんか。
収縮胞は、体内に浸透してきた水分を一時保存し、満たされると収縮して外へ出す器官です。ゾウリムシを使った実験で、マンニトールの薬理作用が目に見えてわかります。もっと知りたければ、いちど私たちと一緒に実験してみませんか。